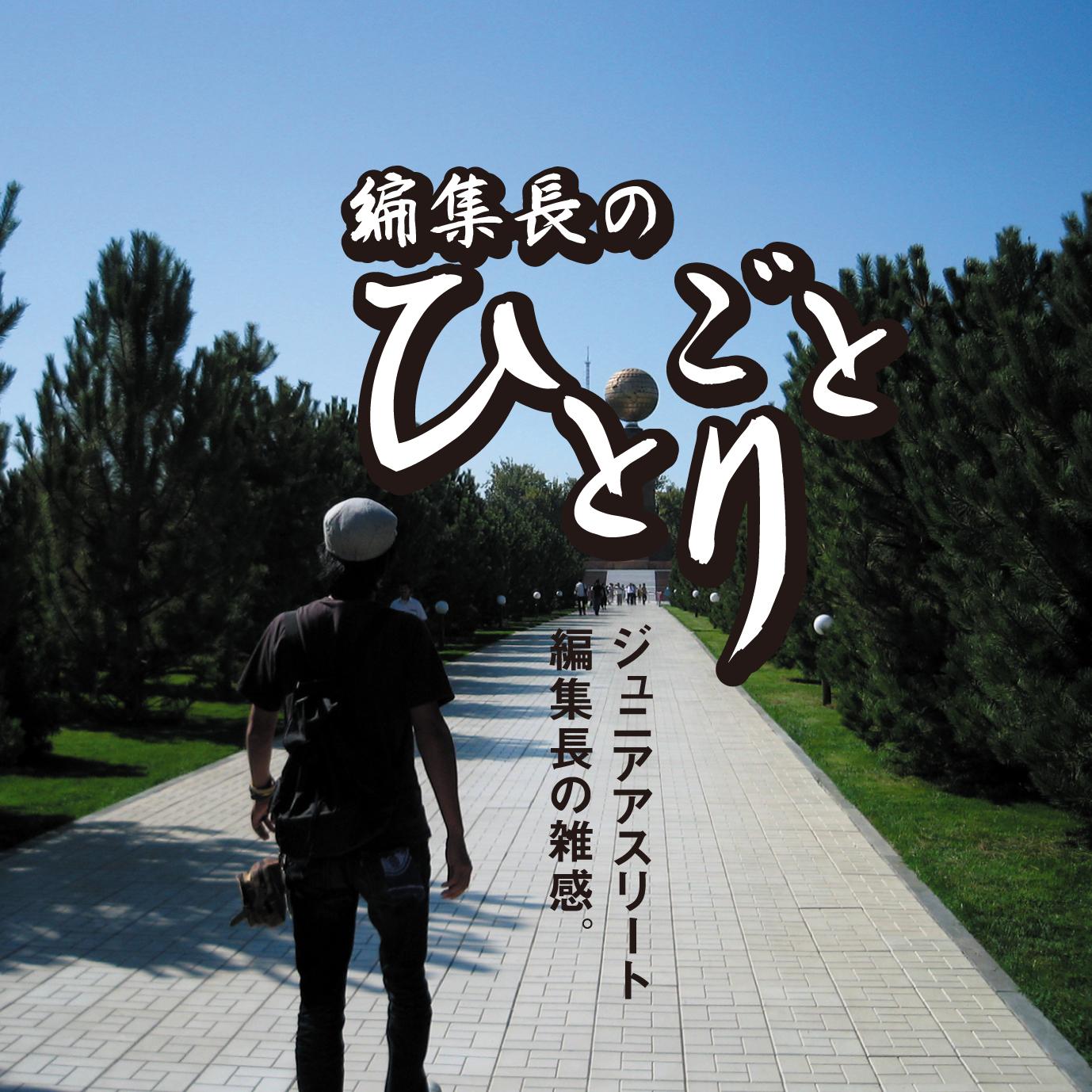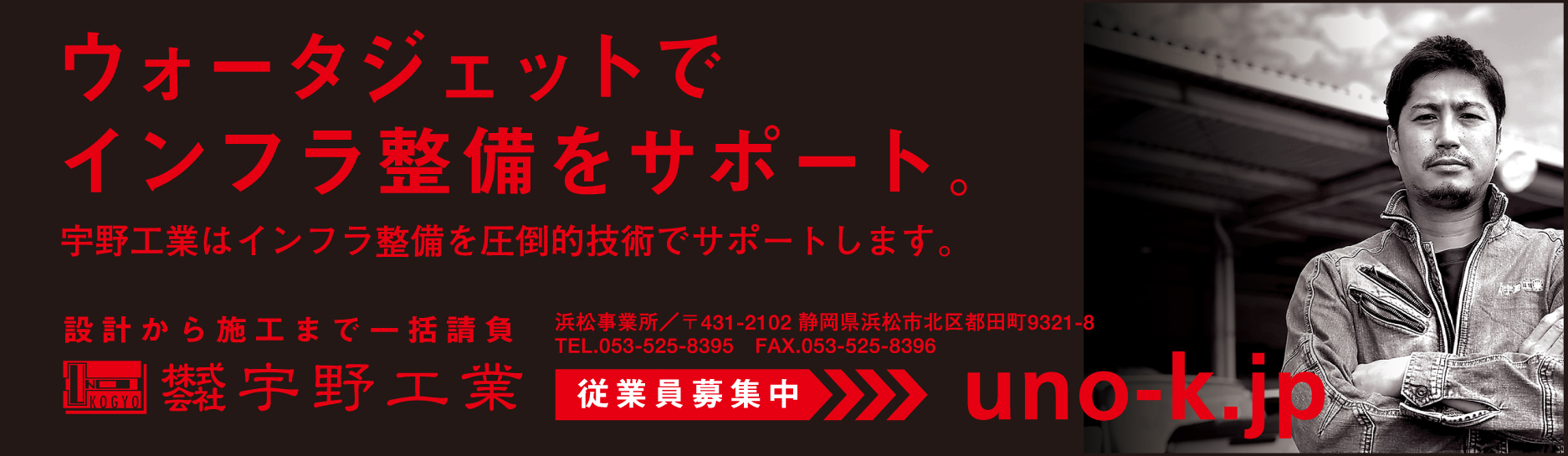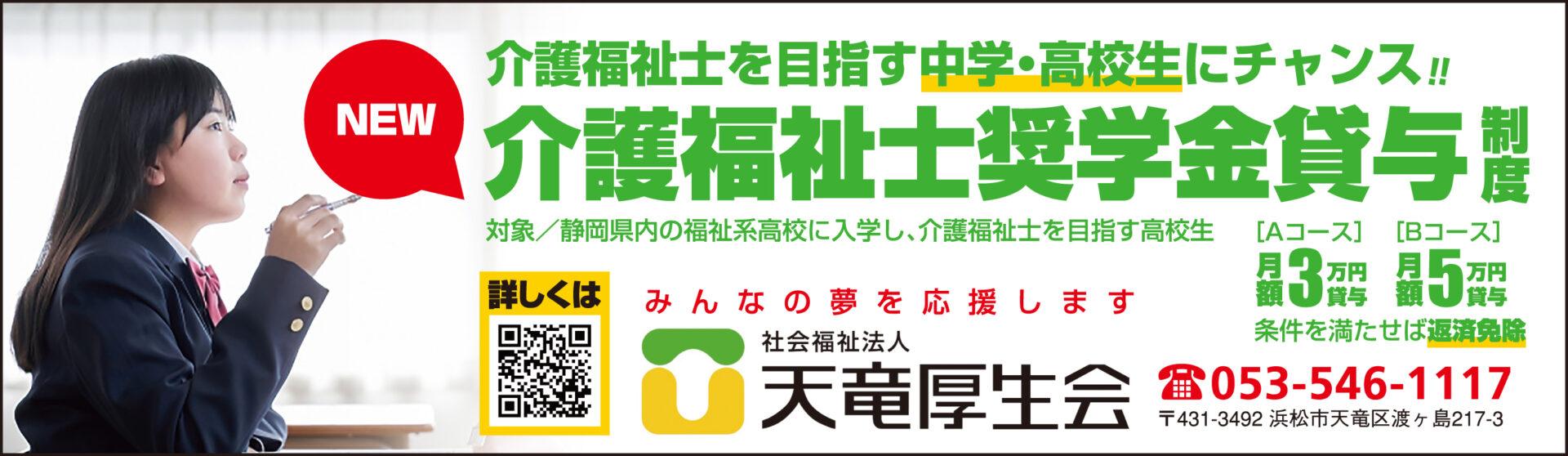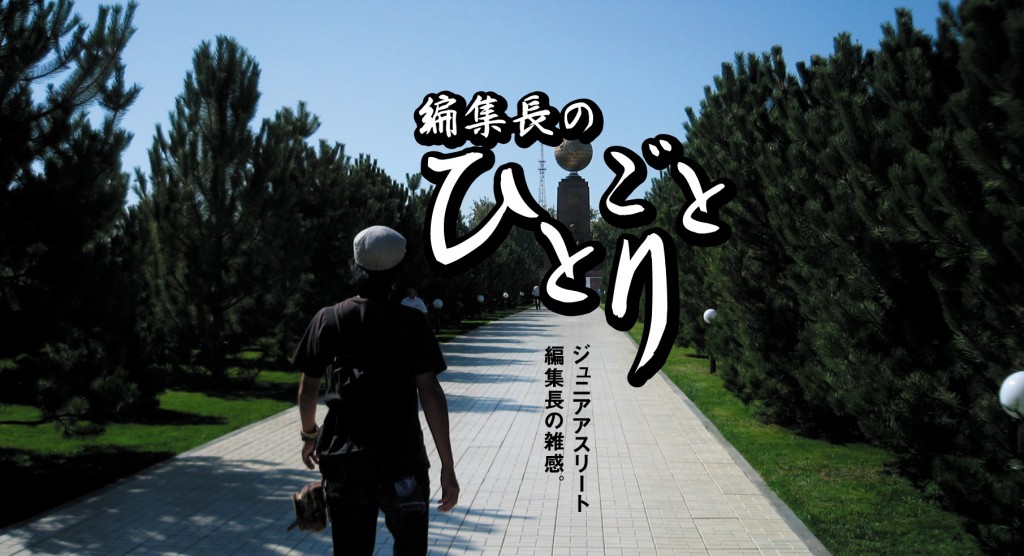赤ちゃんの発育から見る
ケガの原因と予防法。

スポーツをしていれば、ケガをすることも多いと思います。特に学生時代は、多くの人が全力でスポーツと向き合う時期です。成長期ということもあり、身体の変化も著しく、ケガに悩まされることもあると思います。
では、ケガをしてしまったらどうしたらいいのでしょうか。それは、受傷肢位や姿勢や動きをしっかりと評価することが、とても大切になってきます。なぜケガをしてしまったのか。これから、どのように予防していけばいいのかをしっかりと把握することがとても重要です。ここでは、ケガをした原因を見つけるうえで、赤ちゃんの発育・発達に目を向けていきたいと思います。
私たちは、いつの時代も赤ちゃんとして生まれてきます。
赤ちゃんは、立ち上がるまでに一生懸命筋肉を鍛えていることはご存知でしょうか?順を追っていくと、まず大きな声で泣き始め、肺呼吸が始まります。この時、体幹のインナーユニットである横隔膜や骨盤底筋群、腹横筋などが活発に働きます。その後、首が据わると寝返りが始まります。ここでは、胸部の筋肉や胸部回旋の可動域を獲得します。
次に、パピーポジション(うつ伏せに寝て上半身を反らしながら持ち上げる状態)が取れるようになり、体幹部後面の筋肉活動が活発になっていきます。そして、ハイハイができるようになると、肩甲骨や股関節周囲の筋肉が活性化します。
その後、高這い動作をするようになり、足のつま先で地面を蹴ることを覚えます。そして、端座位、そんきょの姿勢を経て立ち上がるようになるのです。立ち始めの頃は、バランスを崩して転ぶことを繰り返しますが、この時に反射的に手を出すことを覚えていきます。このように、赤ちゃんは、立ち上がるまでの間に、様々な筋肉を鍛え、動作を確認し、能力を獲得していきます。
これを踏まえて考えてみましょう。
例えば、前傾姿勢で走っていて転んだとします。前傾姿勢で走るのは猫背になっているからです。姿勢が悪い人の特徴として、体幹のインナーユニットの機能が悪かったり、ハイハイの時期が短く、すぐ掴まり立ちを始めたことで肩甲骨周囲の筋肉が未発達だったりということがあります。転んだことに目を向けると、自立歩行の際に歩行器などでバランスを保っていた人は、転びやすかったり、転ぶ機会が少なかった人は、転んだ時に反射的に手が出ず、大けがをしてしまったりします。
こういったことを把握し、改善することがとても重要です。幼少期に獲得できなかった能力を獲得し、体幹トレーニングを通して、姿勢の改善や、筋力をアップすることで、ケガをしにくい身体づくりや競技パフォーマンスの向上に繋がっていきます。
この機会に自分の幼少期のことを振り返ってみましょう。
そこにあなたを悩ませるケガの原因があるかもしれません。